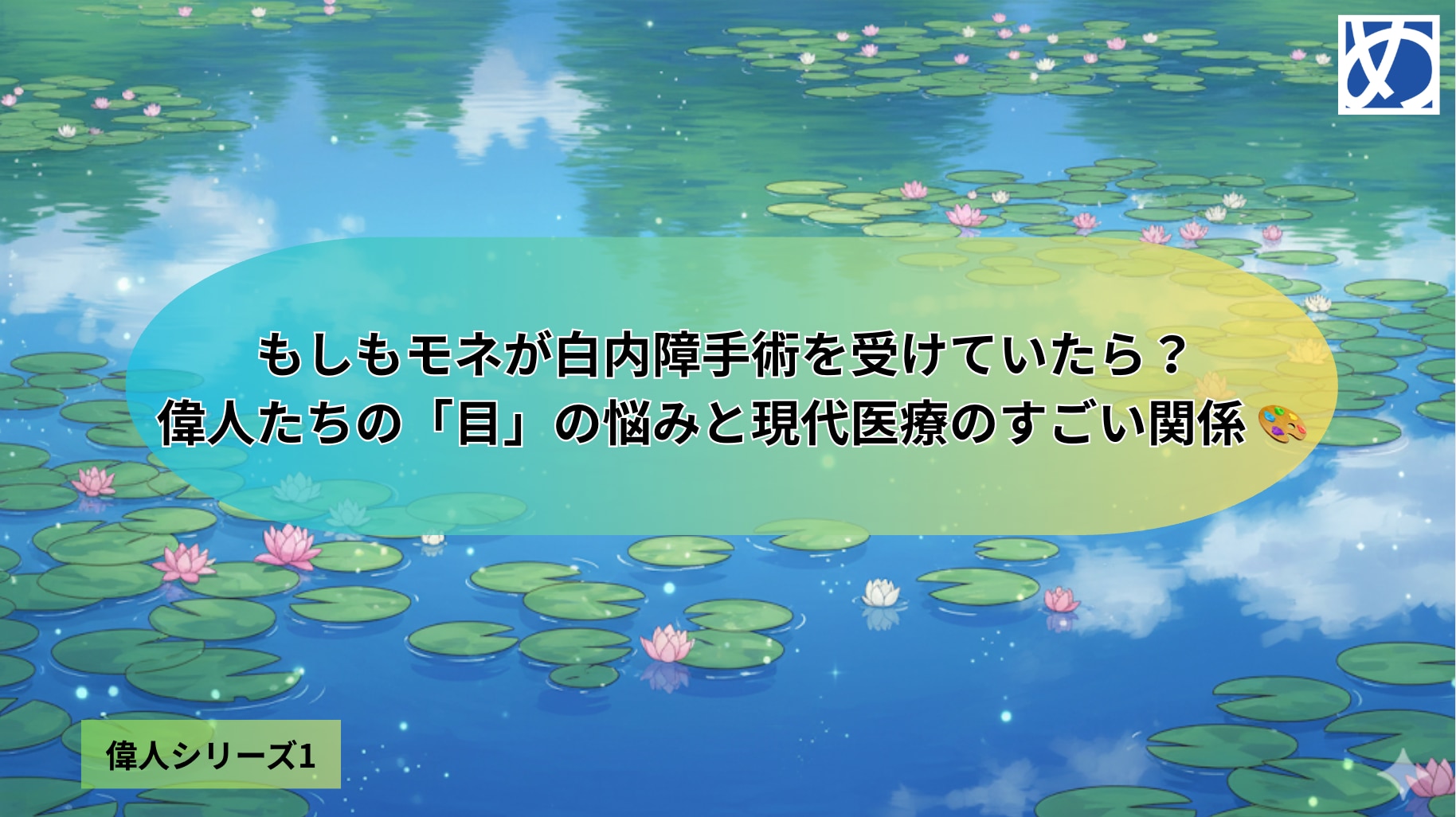
もしもモネが白内障手術を受けていたら? 偉人たちの「目」の悩みと現代医療のすごい関係 🎨
もしもモネが白内障手術を受けていたら? 偉人たちの「目」の悩みと現代医療のすごい関係 🎨
こんにちは!😊
気持ちの良い秋晴れの日が続き、美術館などに足を運びたくなる「芸術の秋」になりましたね。
さて、皆さんは「印象派」を代表するフランスの画家、クロード・モネをご存知でしょうか。
池に浮かぶ睡蓮、ゆらめく水面、やわらかな木漏れ日…。生涯をかけて「光」そのものを描き続け、「光の画家」とまで呼ばれた彼。
しかし、その晩年、彼の目は光を正確に捉えることができなくなっていました。病の名は「白内障」です。
今回は、モネの作品とその「目」の物語を辿りながら、もし彼が現代の眼科医療を受けていたら…?という、時空を超えたお話をしてみたいと思います。
光の画家に忍び寄る「影」
若い頃のモネの絵は、鮮やかな青や緑、繊細な光の表現に満ちています。しかし1912年頃、60代後半になったモネは、目の不調を訴え始めます。
白内障とは、目の中のレンズの役割をする「水晶体」が白く濁ってしまう病気です。
モネの目には、世界がこのように見えていたと考えられています。
- 色が黄色っぽく、濁って見える
- 物の輪郭がぼやけて、二重に見える
- 光を眩しく感じる
光を追い求めた画家にとって、これは死活問題でした。彼は「色彩の感覚が狂ってしまった」と嘆き、多くの作品を自ら破り捨てたと言われています。
白内障は、モネの絵をどう変えたのか
それでもモネは絵を描き続けました。しかし、その作風は病気の進行とともに劇的に変化していきます。
以前の作品と比べると、違いは一目瞭然です。
- 色彩の変化: 青や紫といった涼しい色が消え、赤や黄色、茶色が多用されるようになります。これは、濁った水晶体がサングラスのように青い光をカットしてしまい、赤や黄色が強く見えていたためと考えられています。
- 形の変化: 睡蓮や太鼓橋の形はより大胆で、抽象的になっています。細かい部分が見えにくくなったことで、より感情をぶつけるような激しいタッチへと変化していったのです。
皮肉なことに、この白内障による作風の変化が、後の「抽象画」の誕生に影響を与えたとも言われています。
苦悩の末の「決断」、そして現代へ
視力の悪化に耐えかねたモネは、1923年、ついに片目の白内障手術を受けます。
当時の手術は現代とは比べ物にならないほどリスクが高く、術後も分厚いメガネが必要でした。水晶体というフィルターを失った目で見る世界は、今度は全てが青みがかって見え(青視症)、彼はその見え方にも苦しんだそうです。
もしもモネが、現代の多焦点眼内レンズ手術を受けたら?
では、もしモネが2025年の日本で、私たちのクリニックを訪れたとしたら…?
きっと私たちは、多焦点眼内レンズを使った日帰り手術をご提案するでしょう。
濁った水晶体を取り除き、その代わりに遠くの景色も、中間の水面も、そして手元のパレットも、すべてにピントが合うクリアなレンズを目の中に入れるのです。
手術は10分程度で終わり、痛みもほとんどありません。
分厚いメガネも、老眼鏡も不要です。
彼がもし、術後に若かりし頃のようなクリアで色鮮やかな視界を取り戻していたら…。
一体どんな新しい「睡蓮」を描いたのでしょうか。もしかしたら、全く新しいスタイルの絵画が生まれていたかもしれませんね。
クロード・モネの苦悩は、「見える」ということが、いかに私たちの人生の質(QOL)や、自己表現と深く結びついているかを教えてくれます。
もし、あなたやあなたの大切な人が、色の鮮やかさや、世界の輪郭が失われていくように感じているなら。それは、昔の偉大な画家が苦しんだのと同じ、白内障のサインかもしれません。
幸いなことに、現代の私たちには、彼が手にできなかった「未来」を選ぶことができます。
見え方で気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。





